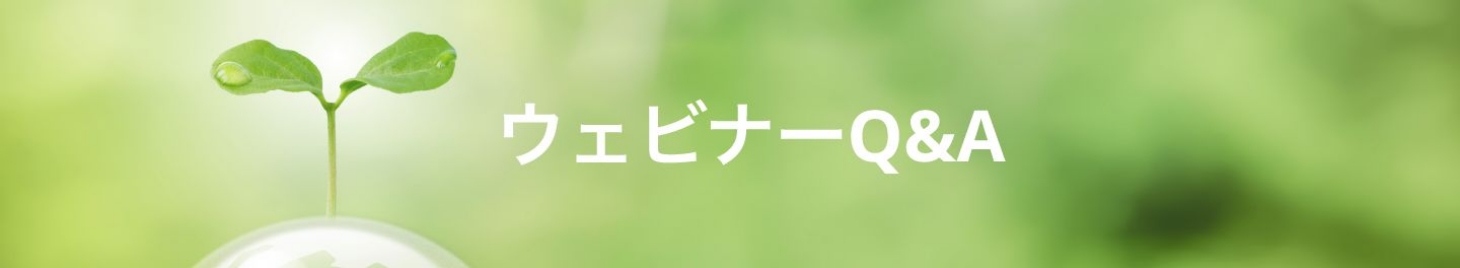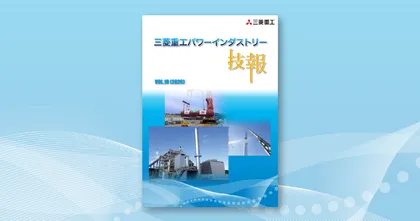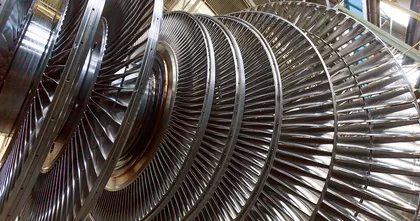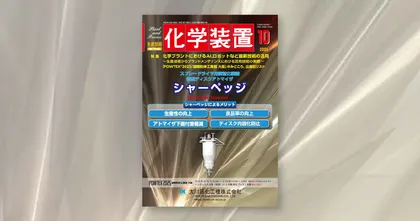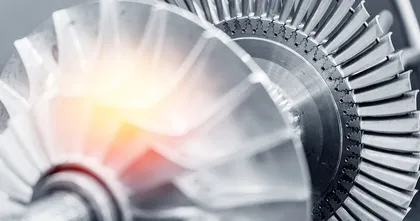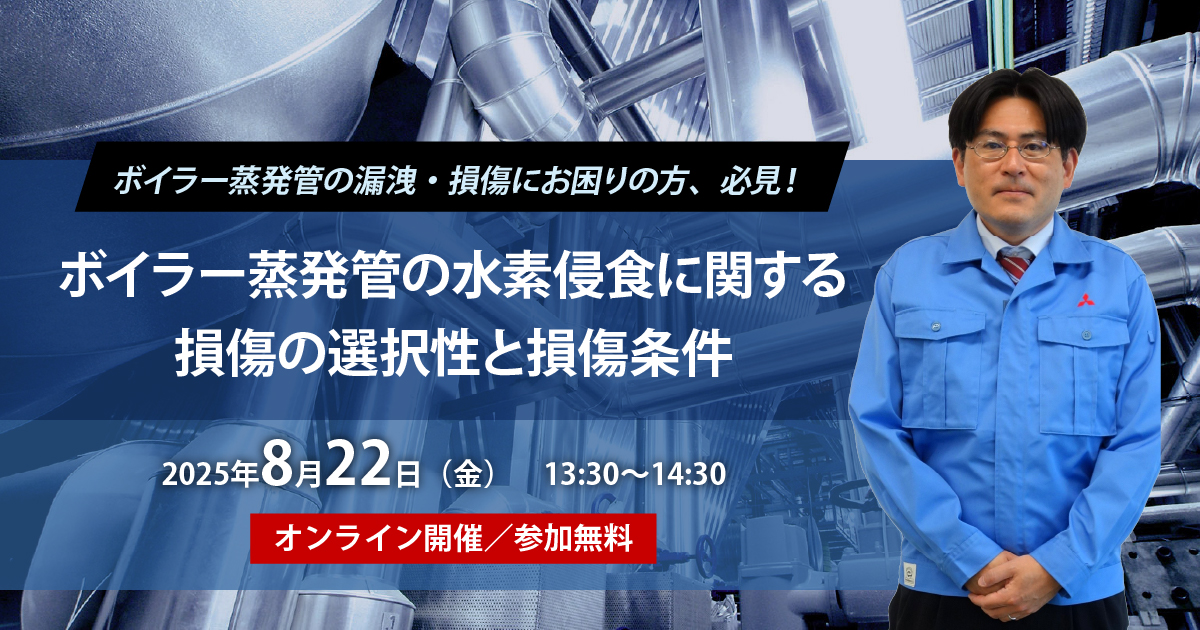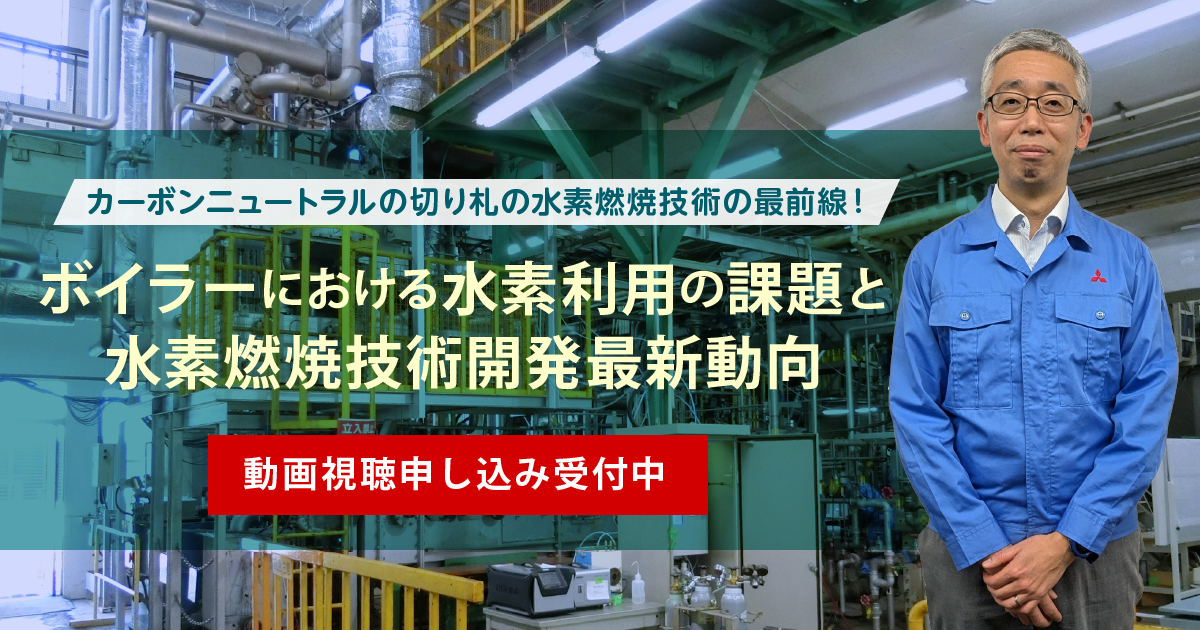ウェビナーでいただいたご質問への回答を掲載しております。皆さまのご参考になれば幸いです。
【2025年8月22日開催ウェビナー】
ボイラー蒸発管の水素侵食に関する損傷の選択性と損傷条件
質問一覧
- 1 今後、水素を燃料とした場合の未燃分も影響しますか。
- 2 水素は100%燃焼しますか。水素ボイラーで未燃の水素が蒸気側に残ることはありますか。
- 3 水素浸食の発生条件だけでなく、発生に至る前の条件や対策、さらにトラブル事例を教えください。
- 4 関連する国際規格(ボイラーにおける水素脆化抑止策など)の動向についてもご教示ください。
- 5 ボイラーの水質調整にアンモニアのみを使用しているのですが、水素侵食が原因と思われる腐食が発生しております。防止対策としてリン酸ソーダの注入は有効でしょうか。
-
6
ウェビナーで説明されていたのは、石炭ボイラー等の形式だと思いますが、回収ボイラーや流動層ボイラーをはじめとする、熱がすぐになくならないタイプのボイラーの場合のリスクについても評価されていますか。
回収ボイラーや流動層ボイラーは、石炭ボイラー等よりも、より厳しく全消火基準を設けるべきなのか指標的な知見があれば、ご教授願いたいと思います。 - 7 ウェビナーで提示されていた高圧ボイラーではなく、清掃工場の廃熱ボイラー(3.0MPaG、300℃程度)でも水素侵食が発生する可能性はありますか。
-
1
- 今後、水素を燃料とした場合の未燃分も影響しますか。
水素侵食の進行(原子状水素の金属内への拡散)のためには、ネルソン線図に示されるような高い水素分圧が必要です。ボイラーの管外面(燃焼場)の圧力は大気圧近傍で低いため、水素を燃料としたボイラーで万一100%未燃の水素が高温で管外面に接触したとしても、管外面の水素侵食の進行の可能性はほぼないものと推定します。
-
2
- 水素は100%燃焼しますか。水素ボイラーで未燃の水素が蒸気側に残ることはありますか。
水素ボイラーの場合、水素は100%燃焼すると考えていただいて結構です。
水素侵食は、管内面側(水側)の管材の腐食で発生する水素による侵食であり、燃料系から管内面側に水素が侵入することはございません。
水素侵食(管内面の腐食)で発生した水素は、溶存水素系で検知できるレベルであり、蒸気系にも移行しますが、蒸気中の濃度は水素侵食の進展場に比べて十分低いため、過熱器管の水蒸気酸化スケールの表面を還元する可能性はあります。しかし、他の部位の管材を侵食するリスクは低いと考えています。 -
3
- 水素浸食の発生条件だけでなく、発生に至る前の条件や対策、さらにトラブル事例を教えください。
水素侵食が発生しやすい環境として、①水質の極端な悪化(特に水中Cl濃度の増加)、②腐食・水素濃縮の形成されやすさ(空隙を持ち、かつ厚い堆積物などが存在)、③一定量の受熱の存在(管材温度が上昇)が考えられます。
-
4
- 関連する国際規格(ボイラーにおける水素脆化抑止策など)の動向についてもご教示ください。
ボイラー蒸発管の腐食防止として、各国際規格とも「運転中のボイラー水のpH低下を確実に防止する」「水処理方式として、リン酸塩処理やアルカリ処理(不揮発性の薬品を使用)を採用する」旨が対策として周知されています。ボイラー水が水質悪化した場合のpHの許容値は、各国により異なります(例:ドイツVGBでは、リン酸塩処理のドラムボイラーでは、9.0を下回ると損傷リスク高まるため、水質改善が必要。8.5を下回ると水質制御不能で深刻な損傷のリスク高のためユニット停止を推奨)。
-
5
- ボイラーの水質調整にアンモニアのみを使用しているのですが、水素侵食が原因と思われる腐食が発生しております。防止対策としてリン酸ソーダの注入は有効でしょうか。
水素侵食は、蒸発管伝熱面での酸(不揮発性)の濃縮が主な原因ですので、ボイラー水にリン酸ソーダ(不揮発性)を注入しておけば、酸の濃縮と同時に濃縮することで濃縮面を中和し、濃縮面のpH低下を抑制できるため、水素侵食の抑制には有効と考えます。
-
6
-
ウェビナーで説明されていたのは、石炭ボイラー等の形式だと思いますが、回収ボイラーや流動層ボイラーをはじめとする、熱がすぐになくならないタイプのボイラーの場合のリスクについても評価されていますか。
回収ボイラーや流動層ボイラーは、石炭ボイラー等よりも、より厳しく全消火基準を設けるべきなのか指標的な知見があれば、ご教授願いたいと思います。
ご認識のとおり、ボイラー消火による水素侵食の抑制は、消火により熱源が速やかに焼失する、一般的な燃焼ボイラーにのみ適用できる方策で、原理的に熱源の速やかな排除ができない回収ボイラーや流動床ボイラーには適用できません。そのため、これらのボイラーについては、ボイラー水のpH管理がより重要になると考えます。
回収ボイラーや流動床ボイラーは運転圧力が15MPa以下ですので、水素侵食に対して耐性の高い、リン酸塩処理を適用し、ボイラー水pHは9.0を下回らない運用を推奨いたします。 -
ウェビナーで説明されていたのは、石炭ボイラー等の形式だと思いますが、回収ボイラーや流動層ボイラーをはじめとする、熱がすぐになくならないタイプのボイラーの場合のリスクについても評価されていますか。
-
7
- ウェビナーで提示されていた高圧ボイラーではなく、清掃工場の廃熱ボイラー(3.0MPaG、300℃程度)でも水素侵食が発生する可能性はありますか。
廃熱ボイラーの場合は、高温排ガスとの対流熱伝達による伝熱であるため、燃焼ボイラーに比べて蒸発管の熱流束が小さくなります。そのため、運転圧力が低い場合には影響はありません。
------------------------------------
Excelファイル 「ボイラー蒸発管水素侵食リスク評価ツール」の申し込み受付は
11月20日(木)をもちまして締め切りました。
たくさんのお申し込みをいただき、誠にありがとうございました。
------------------------------------
※事業・技術上の機微に該当するご質問につきましては、内容の有無にかかわらず記載を控えております。何卒ご理解ください。具体的な事業構想・案件のご相談は、お問い合わせフォームより個別にご連絡ください。